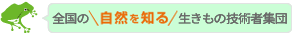私たちが健康診断で病気や注意すべきところを見つけてお医者さんに行くように、まずは、事業所の緑地の状態をチェックしてみませんか。
生きものにとって使いやすい居心地のよい緑地かどうかの健康診断の方法が動植物調査です。これによって、生きものから見た健康状態、すなわち生物多様性の豊かさがわかります。

- JTの森 積丹(積丹川流域エリア/積丹岳地区)の
生態系イメージ
もしかしたら、思わぬところが生きものの重要な生活場所になっているかもしれません。事業所外のみどりの状況はどうですか。あわせて調査をすることで、どんな生きものを事業所の緑地に引き込めるか、どんな配慮をすればより生物多様性を向上させることができるか、考えることができます。